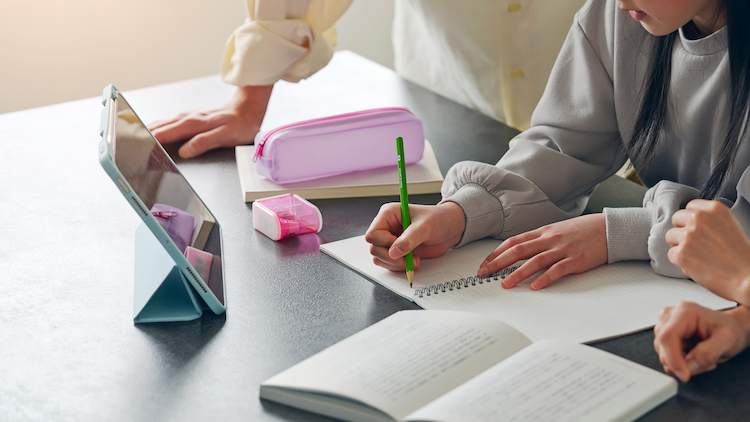「学校に行きたくない」本当の理由と、親ができること【学年別対応】

「子どもが学校に行きたくないと言い出した」
「学校に行くのを渋っている…」
「朝、何かと理由をつけて学校を休もうとしてる」
こんなことでお悩みではありませんか?
「学校に行きたくない」と突然言われても、親御さんにとっては自分の子ども時代には思ってもみなかったことだから、どう対処したらいいのかと悩んでしまいますよね。
そこで今日は、学校に行きたくない子どもの本当の理由と、親御さんができる対対応を、学年別に紹介していきます。
お子さんのSOSに、できるだけ早めに気づき、適切な対処をするための参考にして頂けたら嬉しいです。
お子さんの成績に不安を感じていませんか?
家庭教師のゴーイングには、勉強が苦手なお子さんや不登校・発達障害のお子さんを成績アップに導いてきた経験豊富な先生が揃っています。
ぜひ、ゴーイングのホームページでお住まいのエリアで活躍中の先生をチェックしてみてください!
「学校に行きたくない」本当の理由【学年別】
子どもが学校に行きたくないと感じる理由は、学年や性格、家庭環境などによって様々です。だた、どの子にも共通して言えるのが、初めはなかなか、本当の理由を言ってくれないこと。子どもとしては、自分でもとまどい、「こんなこと言ったら恥ずかしい」「怒られるかも」など、複雑な心境なので、言ってくれるまで待つしかありませんが、理由によって対処の仕方が変わってくるので困ってしまいます。
そこで、小学校1年生から高校生までの子どもの、学校に行きたくない理由を、学年別に具体的に解説していきます。
お子さんの本当の胸の内を知り、適切な対応がとれるようにしてください。
小学校1・2年生の場合
まだ本当に小さいので、社会生活に慣れていない、という大前提があります。
集団生活に慣れていない
初めての集団生活で、友だちとの関わり方や先生の指示に戸惑うことがあります。
お母さんと離れるのが不安
小さい子どもにとって、家族から離れること自体が大きなストレスです。
体調不良や疲れ
朝起きられない、なんとなく体がだるいという理由もあります。実際に体調が悪い場合もありますし、「学校に行きたくない」という気持ちが体調不良として表れることもあります。
先生や友だちが怖い
友だちとのけんかや先生の叱責が原因で、他者に恐怖感を感じることがあります。大人から見ると些細なことでも、子どもにとっては大きな問題です。
小学校3・4年生の場合
小学校中学年になると、人間関係が少しずつ複雑になります。そのため、学校に行きたくない理由も変わってきます。
友だち関係の悩み
グループができ始めるので、友だちと仲良くなれない、仲間外れにされるといった問題が出てくることがあります。
授業がつまらない、わからない
勉強が難しくなる時期なので、学習の困難さにぶつかり始めます。「わからない」という気持ちは、「勉強したくない」に変わることがあります。
叱られることへの恐怖
先生や親から叱られることが怖くて、学校に行きたくないと感じる子どももいます。
習い事や塾で疲れている
学校以外の活動が多すぎて、疲れがたまり、学校に行きたくない、行く気力がでない場合があります。
小学校5・6年生の場合
高学年になると、子どもの悩みは、学年のぶんだけ深刻になることがあります。
思春期の入り口で情緒が不安定
成長期特有のホルモンバランスの変化で、感情が揺れやすくなります。その結果、学校に行きたくない気持ちが強くなることがあります。
いじめや孤立
いじめが顕在化することもあり、クラスで居場所がなくなると、学校が辛い場所になってしまいます。
将来への不安やプレッシャー
中学校を意識し始める時期なので、「勉強しなきゃ」というプレッシャーに押しつぶされてしまう子もいます。
先生と相性が合わない
「この先生が嫌い」「怖い」といった気持ちが、学校や学校生活そのものへの不安につながることもあります。
発達障害の子どもの場合
発達障害を持つ子どもは、特性による理由から困難を感じ、学校に行きたくないと思うことがあります。
感覚過敏
音や光、匂いなどの刺激が強く、教室が苦痛に感じることがあります。
集団行動が苦手
他の子と同じペースで行動することが難しいため、学校が負担になることがあります。
失敗への恐怖
ミスや、他人と比べられることに敏感なため、学校がストレスの源になることがあります。
時間管理や切り替えが苦手
朝の準備や、授業の合間の移動がスムーズにできず、学校で生活すること自体が難しく感じられます。
中学生の場合
中学生になると、思春期に入るので、さらに多くの悩みが生じ、自分自身で悩みを複雑化してしまいます。
友だちや恋愛関係のトラブル
思春期特有の人間関係の悩みが増えます。
勉強が難しくなる
科目が増え、授業内容も高度になるため、ついていけない子どもが増えます。
部活動のプレッシャー
部活での上下関係や競争が辛く、学校全体を嫌に感じることがあります。
親や教師に相談できない
自立したいという気持ちと、助けを求めたいという気持ちの間で葛藤し、一人で悩みを抱え込むことがあります。
高校生の場合
高校生になると、進路の悩みや社会への適応が大きなテーマとなります。
進路へのプレッシャー
大学受験や就職など、将来のことを考え、悩むストレスが強くなります。
校則や教師との衝突
「理不尽」と感じるルールや指導に反発し、学校に行きたくないと感じる子もいます。
友だちとの疎外感
SNSやリアルな友人関係で、孤独感を覚えることがあります。
自由な時間が少ないことへの不満
勉強や部活で忙しく、自由が奪われていると感じる子もいます。
学年別・「学校に行きたくない」場合の対処法
対処法の代表的なやり方を紹介しておきます。どの方法も、子どものトラブルのときには欠かせないやり方ですから、覚えておいてください。
小学生の対処法
小学生の場合は、スモールステップで少しずつ物事を進めていくようにしましょう。子どもなので適応力は思いのほか強く、多少のトラブルは結果的に良い方向へ進むためのきっかけになる場合が多いです。
子どもの話をじっくり聞く
学校で何が起きているのか、子どもが感じている不安を具体的に理解することが第一歩です。
学校の先生と連携する
子どもの状況を担任の先生に伝え、サポートを依頼しましょう。席替えや登校時間の調整など、柔軟な対応をお願いできる場合もあります。
小さな目標を設定する
いきなり学校に行くのが難しい場合、教室の前まで行く、校門まで行くといった小さな目標から始めてみましょう。
成功体験を積ませる
学校以外の場でもいいので、達成感を味わえる機会を作りましょう。自信を取り戻すことで、学校への意欲が湧く場合があります。
中学生の対処法
中学生の場合は、思春期特有の心理や状況を踏まえた対応が必要です。
無理に行かせようとしない
思春期の子どもは、強制されることを嫌がる傾向があります。まずはプレッシャーをかけず、話を聞く姿勢を見せましょう。
学校以外の居場所を探す
フリースクールや地域の学習支援センターなど、学校以外で学べる場所を検討してみましょう。
専門家に相談する
カウンセラーや心理士に相談し、子どもの心理状態を把握するのも有効です。
一緒に解決策を考える
子ども自身が納得できる解決策を見つけるために、一緒にアイデアを出し合う時間を持ちましょう。
高校生の対処法
高校生の場合、成長とともに自立心が高まり、自分の将来を真剣に考えるようになります。子ども自身が自分の未来を描きながら問題を解決していく力を育てることが大切です。
親として支える一方で、子どもを信じて見守り、お子さんの尊厳を傷つけない対応を心がけてください。
進路の悩みに寄り添う
高校生が抱える多くのストレスは、進路や将来への不安からきています。「どんなことに興味があるのか」「将来やりたいことは何か」を一緒に考え、将来へむけて具体的な計画やアクションプランを立て、安心感を与えてあげましょう。
学校以外の選択肢を伝える
「学校に行きたくない」なら、通信制高校や定時制高校、フリースクールなど、学校以外の学びの場があることを教えてあげましょう。「学校に行く」ことだけが選択肢ではないと気づければ、プレッシャーが軽減されます。
適切な休息を提案する
高校生活は勉強や部活で多忙になりがちです。休みが必要なときには無理せず休むことを認め、「今日は少し休んでリフレッシュしよう」と提案してみましょう。
カウンセラーや外部のサポートを利用する
学校のカウンセラーや外部の専門家に相談するのも良いでしょう。親には話せない悩みを持っている場合が多いので、打ち明けやすい環境を整えてあげると、スッとラクになる場合が多いです。
子どもの意見を尊重する
高校生は自分の意志を持つ年齢です。親があれこれと決めつけるのではなく、子どもの考えを尊重し、一緒に解決策を見つける姿勢を持ちましょう。
失敗を受け入れる環境を作る
高校生になると、「失敗したくない」という思いが強くなります。「失敗しても大丈夫」「次にどうするかが大切」と伝え、安心して挑戦できる雰囲気を作りましょう。
SNSやインターネットの影響を把握する
SNSの人間関係や情報の影響で、学校に行きたくないと感じる子もいます。どのような環境で過ごしているのか、さりげなく確認してみましょう。SNS上に不安要素があれば一緒に解決策を考えると良いです。
不登校の理由1位は「学校に行きたくない」ってホント?
文部科学省が公表した調査によると、不登校の主な理由として最も多く挙げられるのが「学校に行きたくない」という気持ちです。ただし、この「学校に行きたくない」という言葉の裏には、実に多様な背景があります。
例えば、友だちとの関係がうまくいかない、授業が難しすぎる、部活動でのストレス、先生とのトラブルなど、具体的な原因が存在します。また、家庭環境や子どもの特性(発達障害や感覚過敏など)も影響を与えることがあります。
「学校に行きたくない」という気持ちを尊重しながら、その理由を深く掘り下げることが、不登校を解決する第一歩になります。
親が「なぜ行きたくないのか?」を理解しようとする姿勢が、子どもに安心感を与えます。
学校を何回休んだらアウトなの?(留年の可能性を解説)
学校を休む回数が増えると、留年の可能性を心配する親御さんも多いと思います。留年とは、実際のところ、「学習内容の理解不足」や「授業時間数の不足」が大きな要因となります。
公立小学校・中学校の場合
公立の義務教育では、基本的に留年することは、ほとんどありません。ただし、長期間の不登校によって学習内容が理解できていない場合、学校側が留年を提案するケースもあります(ごく稀なケースです)。
どのような状況にしろ、学校の先生と定期的に連絡を取り合い、学習の進捗を確認することが重要です。
高校の場合
高校では、一定の授業時間数を出席することが進級の条件となります。一般的には、全授業時間の3分の1以上を欠席すると留年の可能性が高まると言われています。ただし、特別な事情が認められた場合には、補習やレポート提出などでカバーできるケースもあります。
もし長期的に休む可能性がある場合は、早めに学校と相談し、どのように進級を目指すかを一緒に検討すると良いでしょう。
「学校に行きたくない」場合にあらわれる不調のサイン
子どもが「学校に行きたくない」と感じたとき、その気持ちはさまざまな形で身体や行動に現れます。以下に代表的なサインを挙げますので、早めに気づいてあげるようにしてください。
夜眠れない
「学校に行きたくない」というストレスが、夜の不眠として表れることがあります。寝る前にスマホを長時間触るなど、生活習慣が乱れることも要因です。
朝起きられない
ストレスが蓄積すると、朝になると体が動かなくなることがあります。ただの寝坊と思わず、睡眠環境や子どもの心理状態をチェックしてみましょう。
イライラしている
普段より感情が不安定になり、些細なことで怒りっぽくなる場合もあります。これは、学校生活の不安や不満が表面化したサインの一つです。
朝だけ頭痛や腹痛が起こる
朝になると急に体調が悪くなるのは、心因性の症状である可能性があります。このような症状が頻繁に見られる場合は、心療内科や小児科に相談してみるのも選択肢のひとつです。
急にしゃべらない・妙に明るい
黙り込んでしまう、または普段以上に明るく振る舞うのは、子どもなりに「不安」や「行きたくない気持ち」を隠そうとしている場合があります。子どもの微妙な変化に気づき、無理に理由を聞き出さず、そっと寄り添ってあげましょう。
「学校に行きたくない」という気持ちは、多くの子どもが一度は抱くもの。早期に気づけるよう、日頃からお子さんの様子を観察しておこう
「学校に行きたくない」という気持ちは、単なる怠けやわがままではなく、子どもが抱える心の不調や環境の変化のサインであることが多いです。親御さんは、まず子どもの声に耳を傾け、学校でどのような問題が起きているのか、子どもの本音は何かを理解する姿勢を持つようにしましょう。
また、不登校には身体的な不調や精神的なストレスが伴うことがあります。例えば、夜眠れない、朝起きられない、頭痛や腹痛が頻繁に起こるといった症状が見られる場合は、子どもが無理をしている可能性が高いです。こうしたサインを見逃さず、早めに対応してあげると、安心できる環境を整えてあげることができます。
「学校に行きたくない」という気持ちを抱えている子どもに対しては、無理に学校に行かせるのではなく、まずは気持ちを尊重してあげましょう。
また、たとえ学校に通えなくても、家やフリースクールなど、別の居場所で安心して過ごせる時間が作れるようになると、子どもは失ってしまった自信を取り戻しやすくなります。
「学校に行きたくない」という気持ちは、多くの子どもが一度は抱くものです。それが不登校に発展する前に、親御さんが早期に気づき、原因を一緒に考え、解決していこうという姿勢を見せてあげることが大切です。
どの学年でも共通して言えるのは、子どもの気持ちに寄り添いながら、無理なく学校と向き合える環境を整えることです。焦らず、子どもが少しずつ前に進めるようサポートしてあげてください。。